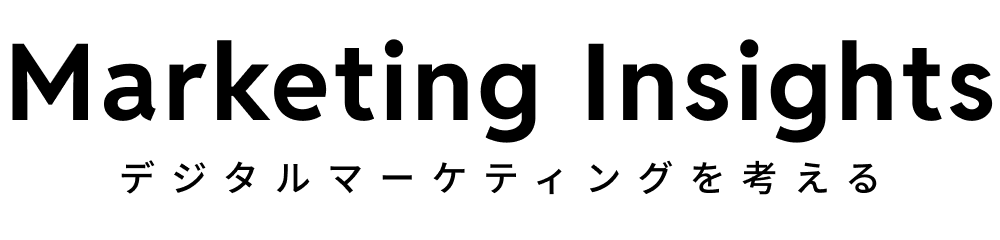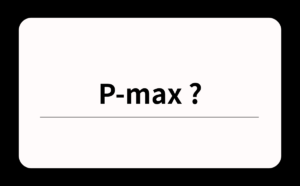ChatGPTがGoogle検索を使っている?
ChatGPTは本当にGoogle検索を使っているのか?実際に検証した記事によると、ChatGPT(Web検索機能が有効になっている状態)はGoogleのインデックスを参照している可能性が高いことがわかりました。本記事ではその検証内容と、SEO・生成AI対策への示唆を解説します。
ChatGPTがGoogle検索を使っている?
以下の複数の検証において、ChatGPT(有料プランでWeb検索機能が有効になっている状態)がGoogle検索のデータを実際に参照していることを検証した事例が紹介されており、ChatGPTは特定の条件下でGoogleの検索インデックスを参照しているものと考えられます。
ChatGPT web search uses Google Search and NOT Bing Search (with proof)
ChatGPT Is Using Google Search – We Tested It
検証の手順
この記事では、以下のような手順でChatGPTがGoogle検索を利用しているかどうかを確かめています。
- 世の中に存在しない新しい単語を作成する
- その単語を説明したページを作成する
- そのページをGoogle検索のインデックスにのみ登録する
- ChatGPTにその単語について説明を求める
- ChatGPTがそのページの内容を元に回答するかどうかを確認する
この実験の結果、ChatGPTがGoogle検索経由でインデックスされたページの情報を参照している可能性が高いことが示されました。
そこから見えること
この結果から考えられるのは、Google検索でのプレゼンスが高いことが、そのままChatGPTの回答に登場しやすさにもつながるという点です。
言い換えれば、SEOで上位表示されることが、最終的にはAIO(Answer Engine Optimization)、LLMO(Large Language Model Optimization)、GEO(Generative Engine Optimization)といった生成AI対策にも直結する可能性がある、ということです。
特別な対策は必要?
少なくとも現状においては、多くの企業が「生成AI対策として特別に新しい施策を行う必要がある」とまでは言えない状況だと考えられます。なぜなら、生成AI特有の傾向(クエリが単語よりも文章的になるなど)はあるものの、最終的には検索結果への対応がAIの回答にも影響を与えるのだとすれば、まずは従来のSEOを優先的に取り組むべきと考えられるからです。
一方で、「すでに特定のカテゴリでSEOにおける圧倒的なプレゼンスを持っている」「検索や生成AIでの表示比率が数%上がるだけでも大きなビジネスインパクトにつながる」といった場合には、生成AI対策を検討する価値があるかもしれません。
また、生成AIが意図と異なる説明をしてしまうケース(例:子ども向けブランドなのに大人向けブランドとして回答されるなど)がある場合、その背景にはWeb上に誤った情報が存在し、それをAIが学習している可能性があります。この場合も本質的な解決策は、正しい情報を整理してコンテンツとして公開し、検索エンジンやAIに正しいシグナルを渡すことにあります。つまり、最終的には基礎的なSEOやコンテンツ作成の重要性に立ち返ることになるのです。
今後のSEO担当者が意識すべきこと
今回の検証からも分かる通り、ChatGPTのような生成AIもGoogle検索の影響を強く受けています。そのため、現時点では「SEO対策こそが生成AI対策でもある」と言えます。では、SEO担当者はどのような点を意識すべきでしょうか?
- 検索での上位表示を引き続き最重要視する
生成AI対策として特別な小手先の手法を考える前に、まずは既存のSEOをしっかりと磨き込むことが重要です。検索結果に出ない情報は、AIの回答にも出にくい傾向があります。 - 高品質で網羅的なコンテンツを作成する
生成AIは断片的な情報を拾うのではなく、Googleが評価した「信頼性の高い情報源」を参照する可能性が高いです。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ作りがより重要になります。 - ユーザーが文章的に質問するケースを想定する
生成AIの利用者は「単語」よりも「文章」で質問する傾向があります。FAQ形式や自然文の検索意図を意識したコンテンツ設計は、SEOだけでなくAIからの引用対策としても有効です。 - 検索以外のチャネルも活用する
BtoBでは特に検索需要が限られるケースもあるため、展示会、ウェビナー、SNSなど検索以外の接点を増やし、AIの学習データに触れる可能性を広げることも大切です。
つまり、少なくとも現状においてはSEO担当者がやるべきことは「生成AI対策」という新しい枠組みを一から考えることではなく、既存のSEOやコンテンツ戦略をより丁寧に実行することなのではないかと考えられます。結果として、それが生成AIにおけるプレゼンス向上にもつながっていくのではないでしょうか。
筆者プロフィール

- ひよっこマーケター
- 外資系テック企業やスタートアップでマーケティングを担当。BtoB・BtoCの両領域を経験。約10年にわたりデジタルを中心にキャリアを積み、オフライン施策も含めてマーケティング活動に幅広く携わっています。短期的なROI改善を目的としたチャネル運用だけでなく、ブランドコンセプトの策定やターゲティング戦略といった中長期的な施策にも取り組んでいます。
最新の投稿
 戦略2026年1月8日デジタルマーケターが取り戻すべき「意思決定」の正体
戦略2026年1月8日デジタルマーケターが取り戻すべき「意思決定」の正体 SEO2025年8月28日ChatGPTがGoogle検索を使っている?
SEO2025年8月28日ChatGPTがGoogle検索を使っている?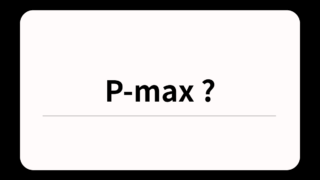 PPC2025年8月25日P-maxとは?仕組みとBtoBリード獲得事例から学ぶROI改善のポイント
PPC2025年8月25日P-maxとは?仕組みとBtoBリード獲得事例から学ぶROI改善のポイント