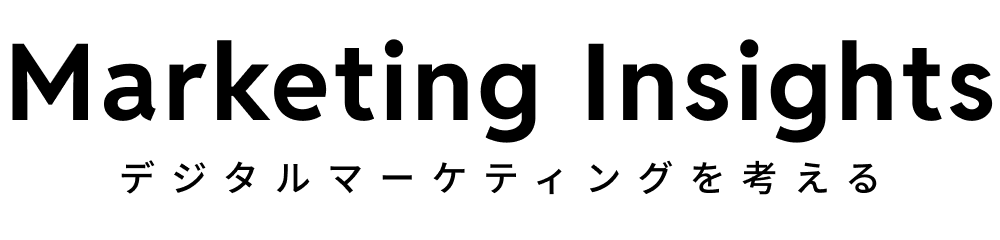P-maxとは?仕組みとBtoBリード獲得事例から学ぶROI改善のポイント
はじめに
P-maxが注目されている背景
近年、Google広告はAIの進化によって大きな変化を遂げています。その代表的な存在が Performance Max(P-max) です。従来の検索広告やディスプレイ広告のように配信先を限定するのではなく、Googleが保有する全チャネル(検索、YouTube、ディスプレイ、Gmail、Discover、マップ)を横断的に活用できる点が大きな特徴です。
私自身も業務の中でP-maxキャンペーンを導入し、従来より高いROIを実現しています。導入前は検索キャンペーンが中心で、キーワードの追加や最適化を行っても成果は頭打ちになっていました。そこで、まずはP-maxを小規模にテストし、効果を確認した上で徐々に予算配分を拡大していきました。
こうした取り組みが成果につながった背景には、ユーザー行動の変化があります。現在は検索だけでなく、動画視聴やSNS的な情報収集、モバイルアプリ利用など、接点が多様化しています。そのため「検索広告だけではユーザー全体を捉えきれない」という課題に対して、P-maxは有力な解決策のひとつと考えられるのです。
本記事で扱う内容(基本解説+事例)
本記事では、まず P-maxの基本的な仕組みや検索広告との違い を整理します。さらに、私自身が実務で経験した BtoBの無料トライアル獲得における活用事例 を紹介し、なぜP-maxが検索広告以上の成果を生み出せたのかを考察します。
単なる機能紹介にとどまらず、実際の運用現場で得られた気づきや、ROI改善の背景にある市場特性についても掘り下げます。
これにより、P-maxをこれから導入しようとしている方、すでに利用しているが活用しきれていない方にとって、 実践的なヒント を得られる内容になっています。
P-maxとは?
定義と概要(Google広告の自動化キャンペーン)
Performance Max(通称:P-max)は、Googleが提供する最新のキャンペーンタイプで、1つのキャンペーンでGoogleの全チャネルに広告を配信できる点が特徴です。対象となるチャネルは、検索、ディスプレイ、YouTube、Discover、Gmail、Googleマップと幅広く、従来は個別に設定していた配信先を統合的に管理できます。
最大のポイントはAIによる自動最適化です。従来の検索広告のようにキーワードを細かく指定したり、ディスプレイ広告のようにプレースメントを選ぶ必要はありません。広告主は「目標(例:無料トライアルの獲得)」「予算」「アセット(テキスト・画像・動画)」を設定するだけで、Googleの機械学習が最適な組み合わせや入札を自動で調整してくれます。
この仕組みにより、従来のキャンペーンではリーチできなかったユーザーにも接触できるため、新しい顧客層の開拓やROI改善につながりやすいのがP-maxの強みです。
配信チャネル(検索・YouTube・ディスプレイ・Gmail・Discover・マップ)
P-maxキャンペーンの最大の特徴は、Googleが保有する複数のチャネルを一括して活用できる点にあります。これにより、ユーザーの多様な行動パターンに合わせて広告を表示し、接点を最大化することが可能です。
- 検索 顕在的なニーズを持ったユーザーに直接リーチできる。購入意欲や比較検討が進んでいる層を獲得するのに有効。
- YouTube 動画視聴中のユーザーに広告を届けられる。ブランド認知や商品理解を深めるために有効で、B2Bでもサービス紹介動画や事例紹介動画が効果を発揮。
- ディスプレイ Webサイトやアプリ上に広告を配信。広範囲に潜在層へアプローチでき、検索広告だけでは拾えないユーザーをカバー。
- Gmail ユーザーの受信トレイに直接広告を表示。メールを通じたリーチは、比較検討中のB2Bユーザーにも有効に働く。
- Discover GoogleアプリやモバイルのDiscoverフィードに広告を配信。興味関心ベースで情報収集する層に自然にリーチできる。
- Googleマップ 店舗や拠点を持つビジネスにおいては、ローカルでの検索・移動中のユーザーに対して広告を表示可能。B2Bでもイベント会場やオフィス所在地の訴求に活用できる。
これらのチャネルを横断的に利用できるのはP-maxならではの強みです。従来のように「検索キャンペーン」「ディスプレイキャンペーン」を個別に運用するのではなく、統合的に管理できることで、より幅広い層に効率的にリーチできるようになります。
検索広告との違い
キーワード依存型 vs データ駆動型
検索広告は「ユーザーが入力したキーワード」に依存して広告を配信する仕組みです。例えば「〇〇 無料トライアル」と検索したユーザーにだけ広告を表示するため、非常に意図が明確で効果的ですが、検索語が存在しない限り広告を出すことはできません。
一方、P-maxはキーワードを中心にした仕組みではなく、Googleが持つ膨大なユーザーデータをもとにAIが配信対象を判断します。検索履歴、閲覧履歴、動画視聴、アプリ利用など多面的なシグナルを解析し、コンバージョンの可能性が高いユーザーを見つけ出して広告を届けます。
この「キーワード依存型」と「データ駆動型」という根本的な違いが、P-maxの拡張性と成果の高さにつながっています。
顕在層だけでなく潜在層も獲得できる点
検索広告は、すでに課題やニーズを認識して「調べている人=顕在層」に強くアプローチできます。しかし、まだ課題を自覚していないユーザーや、解決策を探していない「潜在層」には基本的にリーチできません。
P-maxはGoogleの複数チャネルを通じて、動画やディスプレイ、Discoverなど検索以外の接点でも広告を配信できるため、顕在層に加えて潜在層にも効率的にリーチできます。例えば、まだ「具体的なキーワード検索はしていないが、関連する情報を閲覧している」ユーザーに広告を表示し、興味を喚起してからトライアルや購入につなげることが可能です。
このように、P-maxは顕在層獲得に加えて新しい見込み顧客層を広げることができるため、広告全体のROI向上に貢献します。
なぜP-maxが効果的なのか?
データ量とAI学習
P-maxが効果を発揮する大きな理由のひとつが、Googleが持つ膨大なデータとAIによる学習です。検索行動だけでなく、Web閲覧履歴、YouTubeの視聴傾向、アプリ利用状況といった多様なデータが統合され、広告配信に活用されます。これにより、単一チャネルだけでは得られない深いインサイトをもとに、コンバージョン可能性の高いユーザーを見極められるようになります。
検索キャンペーンでもAIはすでに活用されています。例えば自動入札(Smart Bidding)やレスポンシブ検索広告などでは、機械学習が成果を最適化しています。ただし検索キャンペーンの場合、学習の中心は検索クエリやクリック履歴といった検索行動データに限られています。これに対してP-maxは、検索に加えてYouTubeやディスプレイ、Discoverなど複数チャネルのデータを統合的に活用できるため、より幅広いユーザー行動をもとに最適化が行われます。この「データの幅と統合度」の違いが、P-maxが検索広告以上に効果を発揮しやすい理由のひとつです。
クリエイティブの自動最適化
P-maxでは広告主が用意したテキスト、画像、動画といったアセットを組み合わせ、AIが自動で最適化して配信します。ユーザーごとに最適なクリエイティブが生成されるため、同じアセットでも接触するタイミングやチャネルに応じて訴求力を最大化できます。これにより、従来のように細かく広告セットを分けなくても、多様なユーザーに合わせた効果的なメッセージを届けられます。
ユーザー単位の入札最適化
検索広告ではキーワード単位で入札戦略を考えるのが基本ですが、P-maxはユーザー単位で「このユーザーはコンバージョンする確率が高い」とAIが判断し、リアルタイムで入札を調整します。同じキーワードでもユーザーによって入札額が変わるため、無駄なクリックを減らし、効率よく予算を使えるのが特徴です。
コンバージョン確率の推定には、検索履歴や広告接触だけでなく、YouTubeの視聴傾向、アプリ利用、閲覧しているページのカテゴリ、さらには時間帯やデバイス、場所といった多様なシグナルが用いられており、それをAIが総合的に解析します。これにより、単に「どのキーワードで検索したか」ではなく、「そのユーザーが今コンバージョンする可能性がどのくらい高いか」を予測し、ユーザー単位で入札を最適化できるのが大きな特徴です。
BtoB無料トライアル獲得における事例
課題:検索広告だけでは獲得数が頭打ちに
とあるBtoB SaaSプロダクトの無料トライアル獲得において、検索キャンペーンを出稿していたが、キーワードを追加・変更しても大きく成果が伸びず、CPAが高止まりしてしまう課題がありました。検索広告は顕在的なニーズを持つユーザーに対しては強力ですが、検索ボリュームが限られる市場ではどうしてもインプレッションや獲得件数に上限がありました。
施策:P-maxへの予算比率を増加
そこで新たにP-maxを導入し、まずは少額からテストを実施。成果が確認できた段階で徐々に予算比率を拡大していきました。検索広告と比較して幅広いチャネルに広告を出せるため、潜在的な層にもリーチが広がり、新しい獲得経路を作ることができました。
具体的な設定としては、コンバージョン目標を「無料トライアル登録」に置き、ターゲットROASを設定せずにまずはコンバージョン数最大化で配信を開始しました。アセットはテキスト広告文(サービスの訴求コピー)、ディスプレイ用のバナー、そして簡単な紹介動画を用意し、Googleのアセットグループで自動的に組み合わせを最適化。さらに、既存顧客リストや過去のサイト訪問ユーザーをオーディエンスシグナルとして設定し、AIが学習を開始しやすいように工夫しました。
結果:獲得件数増加+CPA改善でROI向上
その結果、検索広告単独のときよりも獲得件数が増加し、CPAも改善。ROI全体が向上しました。特に、検索では拾えなかった潜在層からの流入がコンスタントに増えたことが成果に直結したポイントです。
潜在層からの流入が増えたかどうかは、次のような方法で確認することができます。ひとつは Google広告のインサイトレポート で「新規ユーザー獲得数」や「オーディエンスカテゴリ別の成果」を確認することです。もうひとつは GA4(Google Analytics 4)の新規訪問ユーザー割合や初回訪問からのコンバージョン数 を計測する方法です。これらを見比べることで、「検索では流入していなかった層が、ディスプレイやYouTube経由で初めてサイトを訪問し、トライアルに至っている」ことがデータとして裏付けられます。
考察:なぜ成果が改善したのか
BtoB市場の検索ボリューム
1つには、BtoB商材は、BtoCに比べて検索需要が限定的な傾向があるのではないかと推察しています。たとえば「スマホ」や「旅行」といったBtoC商材は数百万〜数千万規模の消費者が検索しますが、「人事評価システム」「製造業向けERP」といったBtoB商材は、実際に検索するのは対象業務に関わる一部の担当者に限られます。そのためまずシンプルに検索ボリュームが小さいこと。
さらにBtoBの購買プロセスは、個人で購買判断ができるBtoCと異なり、情報収集 → 社内検討 → 稟議承認 → 最終選定という長いステップを経るため、検索はあくまで情報収集の一部に過ぎず、展示会や営業からの紹介、ホワイトペーパーのダウンロードなど、検索以外のチャネルも大きな役割を果していると考えられます。そのため、購買行動において検索の依存度が低いということが考えられます。
BtoBは単価が大きいため、少数のリードでもROIが成立するケースは多くあります。しかし検索広告だけに依存すると、リード数の安定性に欠けたり、成長余地が限られたりする課題があります。そのため、潜在層まで広くカバーできるP-maxを活用することで、中長期的なパイプライン形成につなげることができます。
P-maxが検索広告の弱点を補完した
今回の事例で成果が改善した背景には、検索広告ではリーチできなかった潜在層にP-maxがアプローチできていた可能性があります。検索広告は「課題を自覚してすでに調べている顕在層」に強い一方で、それ以外の層には届きにくい傾向があります。
一方で、P-maxはYouTubeやディスプレイ、Discoverなど検索以外のチャネルにも配信されるため、情報収集中の段階や、まだ具体的な解決策を探していない段階のユーザーに触れていた可能性があります。たとえば「業務改善」「コスト削減」といった広いテーマに関心を持つユーザーに広告が表示され、そこから認知や興味につながったのではないかと推測されます。
また、オーディエンスシグナルとして既存顧客やサイト訪問者データを活用したことにより、AIが類似傾向を持つ新規ユーザーを見つけやすくなったとも考えられます。これらが組み合わさり、「検索では獲得しづらい層」から安定的な流入が生まれた可能性があり、それが全体のROI改善につながったと考えられます。
筆者プロフィール

- ひよっこマーケター
- 外資系テック企業やスタートアップでマーケティングを担当。BtoB・BtoCの両領域を経験。約10年にわたりデジタルを中心にキャリアを積み、オフライン施策も含めてマーケティング活動に幅広く携わっています。短期的なROI改善を目的としたチャネル運用だけでなく、ブランドコンセプトの策定やターゲティング戦略といった中長期的な施策にも取り組んでいます。
最新の投稿
 戦略2026年1月8日デジタルマーケターが取り戻すべき「意思決定」の正体
戦略2026年1月8日デジタルマーケターが取り戻すべき「意思決定」の正体 SEO2025年8月28日ChatGPTがGoogle検索を使っている?
SEO2025年8月28日ChatGPTがGoogle検索を使っている?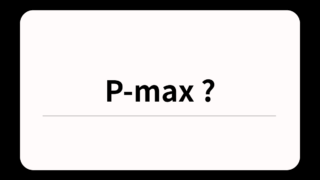 PPC2025年8月25日P-maxとは?仕組みとBtoBリード獲得事例から学ぶROI改善のポイント
PPC2025年8月25日P-maxとは?仕組みとBtoBリード獲得事例から学ぶROI改善のポイント